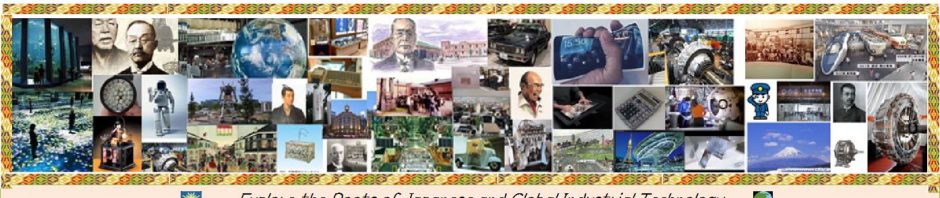―日本の時計の進化の技術発展の足跡を体感ー
 今年、東京墨田区にあるセイコーミュージアムを再び訪ねた。この記事は、このときの印象と見聞録。 セイコーミュージアムの施設は、東武線の向島駅から歩い
今年、東京墨田区にあるセイコーミュージアムを再び訪ねた。この記事は、このときの印象と見聞録。 セイコーミュージアムの施設は、東武線の向島駅から歩い て10分ほどの隅田川沿いにあり、近くには向島百花園などがあって季節には散歩に丁度良い場所でもある。博物館を訪ねるため隅田川の白髭橋近づくと巨大な壁面時計の目立つビルディングがみえた。これがセイコーミュージアムである。 このセイコーミュージアム (旧セイコー時計資料館) は1981年、創
て10分ほどの隅田川沿いにあり、近くには向島百花園などがあって季節には散歩に丁度良い場所でもある。博物館を訪ねるため隅田川の白髭橋近づくと巨大な壁面時計の目立つビルディングがみえた。これがセイコーミュージアムである。 このセイコーミュージアム (旧セイコー時計資料館) は1981年、創 業100周年記念事業として設立された。この博物施設は2012年4月にリニューアルを行って展示が大幅拡大し、時計の進化の歴史、和時計、セイコーの歴史・製品の展示、スポーツ計時体験コーナーなどを設けて時計技術の紹介を行う本格的な産業博物館となっている。ミュージアムは地上三階の建物で、一階フロアは、内外の時計の歴史を
業100周年記念事業として設立された。この博物施設は2012年4月にリニューアルを行って展示が大幅拡大し、時計の進化の歴史、和時計、セイコーの歴史・製品の展示、スポーツ計時体験コーナーなどを設けて時計技術の紹介を行う本格的な産業博物館となっている。ミュージアムは地上三階の建物で、一階フロアは、内外の時計の歴史を
展示するコーナー、二階はセイコー社の歴史と歴代のセイコー時計製品を展示され、これに併せて日本の江戸時代以前に使われた「和時計」が数多く収集展示されている。三階は図書館と事務所・会議室などである。また、このミュージアムは、インターネットでみられる、「バーチャル・ツアー」
(http://museum.seiko.co.jp/virtual/) や「セイコー」の製品群や技術背景を紹介する動画なども用意されていて利用には便利である。
(注)訪問時、セイコーミュージアムは東京都墨田区に設けられていたが、2020年8月、中央区銀座に移転して新装開館「セイコーミュージアム銀座」となっている。新施設には、まだ行っていないが、近く訪問して見学報告をするつもり。
○ セイコーミュージアム銀座:〒104-0061東京都中央区銀座4丁目3-13
セイコー並木通りビル HP: https://museum.seiko.co.jp/
♣ 展示の内容と時計の歴史
一階の展示室に入るとまず目に入るのは、紀元前から使われていた時刻の推移を示すために作られ ていた古代の「日時計」であった。紀元前3000年前後のものだという複製であるが、当時の姿をよくとどめている。この時代から「暦」や「時刻」は天然現象や生産
ていた古代の「日時計」であった。紀元前3000年前後のものだという複製であるが、当時の姿をよくとどめている。この時代から「暦」や「時刻」は天然現象や生産 活動と結びつけて政治の重要事項であったことが分かる。また、同じ展示コーナーには、各地で古くから使われた日時計、砂時計、水時計などの模型があり興味を引く。中には、中国北宋時代に使われていたという水時計「水運儀象台」の縮小模型も展示だれており、天文観測による皇帝政治の重要な用具として用いられていたとの解説も付されている。
活動と結びつけて政治の重要事項であったことが分かる。また、同じ展示コーナーには、各地で古くから使われた日時計、砂時計、水時計などの模型があり興味を引く。中には、中国北宋時代に使われていたという水時計「水運儀象台」の縮小模型も展示だれており、天文観測による皇帝政治の重要な用具として用いられていたとの解説も付されている。
 日本では、江戸時代に「線香時計」という、線香の燃える早さで時間を計ったという面白いものも展示の中に見られる。いずれにしても、機械式時計が生まれる前、日光や砂、水といった自然物をつかった時刻をしめす道具として長い間人々に用いられていたことが分かる。
日本では、江戸時代に「線香時計」という、線香の燃える早さで時間を計ったという面白いものも展示の中に見られる。いずれにしても、機械式時計が生まれる前、日光や砂、水といった自然物をつかった時刻をしめす道具として長い間人々に用いられていたことが分かる。
機械時計が振り子を利用した形で生まれたのは13世紀頃以降であるようだが、博物館には1500年頃作られた「鉄枠塔時計」が展示されているが、これが最古の機械式時計と同じ構 造であるという。また、この展示コーナーには、1700年頃の「ランタンクロック」、1800年代の振り子時計「ビッグベン時計塔時計」のプロト
造であるという。また、この展示コーナーには、1700年頃の「ランタンクロック」、1800年代の振り子時計「ビッグベン時計塔時計」のプロト タイプ、フランスで作られた工芸的な懐中時計「からくり押打ち鍵巻懐中時計」(1800s) など、時計の歴史を見る上で貴重な展示品が数多く並べられており勉強になる。
タイプ、フランスで作られた工芸的な懐中時計「からくり押打ち鍵巻懐中時計」(1800s) など、時計の歴史を見る上で貴重な展示品が数多く並べられており勉強になる。
18世紀のフランス貴族が珍重した装飾時計、大時
 計などにも眼が離せない。世界にこんなに多くの種類の時計
計などにも眼が離せない。世界にこんなに多くの種類の時計 があったのかと改めて感心させらる。時を計るという文化が如何に普遍的で、人間生活にとって重要であったかというこ
があったのかと改めて感心させらる。時を計るという文化が如何に普遍的で、人間生活にとって重要であったかというこ
とを痛感できる。
♣ 展示に見る「和時計」と日本の時計文化
この博物館展示のうちなんといっても圧巻なのは、「和時計」展示であろう。このミュージアムに
 は、この江戸時代を中心に当時の工・芸技術の粋を集めた日本仕様の歴史的な機械時計が数多く展示されてい
は、この江戸時代を中心に当時の工・芸技術の粋を集めた日本仕様の歴史的な機械時計が数多く展示されてい
 る。
る。
ちなみに、日本に初めて機械式の時計がもたらされたのは、1
7世紀ポルトガルであったと言われるが、その後、日本独自の工夫と技術を加え、日の出から日没までの時間を 分割して時を告げる“不定時制”による「和時計」製作となった。これは美術品としても珍重され改良が加えられ様々な形の時
分割して時を告げる“不定時制”による「和時計」製作となった。これは美術品としても珍重され改良が加えられ様々な形の時 計が創られた。それらは現在の眼で見ても感心させられる精巧な機械装置を持っており、芸術性の高い時計である。明治以降は、太陽暦となって「和時計」自体は制作されなくなったが、そこで培われた機械加工の技能は次代にひきつがれたと見られている。
計が創られた。それらは現在の眼で見ても感心させられる精巧な機械装置を持っており、芸術性の高い時計である。明治以降は、太陽暦となって「和時計」自体は制作されなくなったが、そこで培われた機械加工の技能は次代にひきつがれたと見られている。
♣ 日本の時計製作の歴史とセイコー
「時制」が西洋式の太陽暦になって以降の明治に作られた多くの時計は、新たな西洋技術を取り入
 れたゼンマイ動力や歯車、振り子を使う方式ものに切り替わったが、これに挑戦する明治日本の時計メーカーが数多く生まれ、争って参入して、社会「近代化」の一翼を
れたゼンマイ動力や歯車、振り子を使う方式ものに切り替わったが、これに挑戦する明治日本の時計メーカーが数多く生まれ、争って参入して、社会「近代化」の一翼を になう時計づくりが進行した。
になう時計づくりが進行した。
この日本の時計づくりの中にあって、主導的な役割を果たしたのが、「服部時計店」、今のセイコーの前身である。博物館の二階には、このセイコー社の歩んだ時計づくりの沿革が実話を交えながら紹介され、日本の時計産業がどのような経過をたどったのかよくわかる。特に、創業者服部金太郎の技術経営者としての事跡の展示は印象深い。 また、セイコーの製品群も時を追ってどのように変化し、技術が進展したかも展示品から読み取れる。大きな振り子時計、家庭の時を告げる柱時計、初期の懐中時計、そして精巧な腕時計へと進展する技術の発展経過は製品群の中に体現されている。これらを、展示品の実物を見ながら時間軸を追って確認できるのは楽しい。この中でも、日本の機械技術の高い水準が示されたのは「クオーツ」時
また、セイコーの製品群も時を追ってどのように変化し、技術が進展したかも展示品から読み取れる。大きな振り子時計、家庭の時を告げる柱時計、初期の懐中時計、そして精巧な腕時計へと進展する技術の発展経過は製品群の中に体現されている。これらを、展示品の実物を見ながら時間軸を追って確認できるのは楽しい。この中でも、日本の機械技術の高い水準が示されたのは「クオーツ」時 計の開発であろう。このクオーツによって時計は機械時計では考えられなかった正確さ示し、日本の腕時計が世界の市場で主導権を握るまでになった。博物館では、このク
計の開発であろう。このクオーツによって時計は機械時計では考えられなかった正確さ示し、日本の腕時計が世界の市場で主導権を握るまでになった。博物館では、このク オーツがどのように開発され、どのようなメカニズムになっているかが詳細に説明されている。また、この結果、デジタル時計の普及を招き、大衆商品化され、時計が今まで以上に身近なものになった。今や時を告げる時計は、身の回りのアクセサリーである。
オーツがどのように開発され、どのようなメカニズムになっているかが詳細に説明されている。また、この結果、デジタル時計の普及を招き、大衆商品化され、時計が今まで以上に身近なものになった。今や時を告げる時計は、身の回りのアクセサリーである。 時計そのものについてみれば、クオーツによって日本のメーカーが一度は世界を席巻するが、近年になると、デザイン性の高い機械時計の価値が見直され、スイスなどの時計マイスターによる高級時計がハイエンド市場で愛好される結果となっている。日本の時計メーカーは「数は売れるが」、売り上げや付加価値、ブランド性ではスイスなどのメーカーに後れをとる結果となっていて残念である。しかし、セイコーなども、クオーツと機械時計の長所や太陽電池駆動等の機能面で優れた「グランドセイコー」などの高級ブランド製
時計そのものについてみれば、クオーツによって日本のメーカーが一度は世界を席巻するが、近年になると、デザイン性の高い機械時計の価値が見直され、スイスなどの時計マイスターによる高級時計がハイエンド市場で愛好される結果となっている。日本の時計メーカーは「数は売れるが」、売り上げや付加価値、ブランド性ではスイスなどのメーカーに後れをとる結果となっていて残念である。しかし、セイコーなども、クオーツと機械時計の長所や太陽電池駆動等の機能面で優れた「グランドセイコー」などの高級ブランド製 品を生み出しており、ハイエンド市場でも復権の兆しが見られる。
品を生み出しており、ハイエンド市場でも復権の兆しが見られる。
時計という機械製品の歴史的な発展の姿を見ることを通じて、技術がどのように変化していくものなのか、製作者の姿勢や社会変化がどうものづくりに関わるか、技術の継承と時代変化など、多くを感じさせられる時計博物館訪問であった。